シンクライアントとは? メリットとデメリット、実行方式を解説
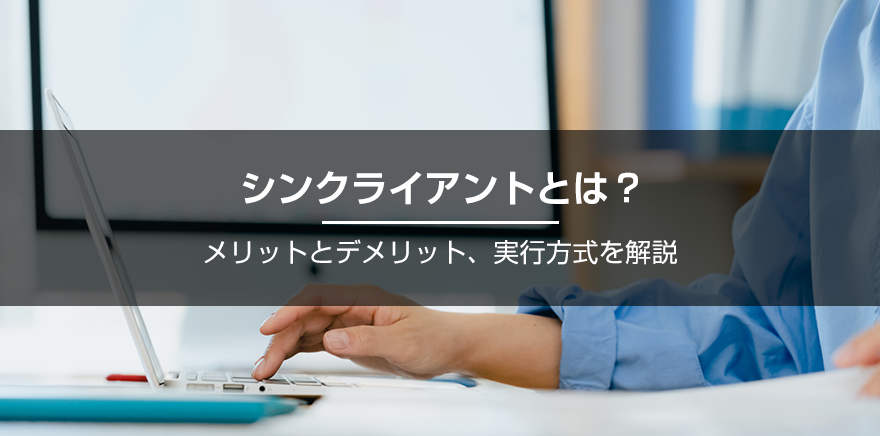
シンクライアントの導入には、リモートワークが可能になったり、災害などによってオフィスが被害を受けても業務を継続できたりと、多くのメリットがあります。一方で、事前に把握しておきたいデメリットも存在します。
今回は、シンクライアントとは何か基本的な概要を解説し、メリット・デメリットや実行方式について詳しく解説します。企業でリモートワークを推進する場合は、ぜひ参考にしてみてください。
シンクライアントとは

シンクライアントとは、クライアント端末に最低限の機能のみを備え、主な処理やデータ管理をサーバー側で実行するシステムを指します。「Thin(薄い・厚みが無い)」と「Client(サーバーから情報やサービスを受け取るコンピューター)」を組み合わせた言葉です。
シンクライアントは通常、クライアント端末に大容量の記憶媒体(HDDやSSD)は搭載されず、アプリケーションもインストールされません。端末は入出力装置(キーボード、マウス、ディスプレイ)として機能し、アプリケーションの実行やデータ処理はすべてサーバー側で実行します。
シンクライアントでは、データがクライアント端末に保存されないため、紛失や盗難による情報漏洩リスクが低く、テレワーク環境での利用にも適しています。
シンクライアントのメリット

ここでは、シンクライアントのメリットを4つ紹介します。
メリット① 運用管理コストの低減
従来のPC環境では、各端末に対して個別にアプリケーションのインストールやアップデート、セキュリティ対策を実施する必要がありました。
しかし、シンクライアントではアプリケーションやデータがサーバー側で一元管理できるため、情報セキュリティ部門の担当者が端末を1つずつメンテナンスする手間が省けます。
その結果、運用保守に必要な人員や時間が削減され、管理にかかるコストを低減できる点がメリットです。特に、企業規模が大きく端末の数が多い場合には、この効果はさらに顕著になり、大規模なシステムを効率的に管理できます。
メリット② 場所を選ばない
シンクライアントは、インターネットの環境があれば場所を選ばずに利用できる点がメリットです。ユーザーはオフィスに限らず、自宅や外出先など、どこからでもサーバーにアクセスして仕事ができるため、リモートワークに適しています。
さらに、シンクライアントはSSL通信によってデータが暗号化されており、セキュアな状態でアクセスできるため、外部からの接続でも安全性が確保されています。情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら柔軟に働くことが可能です。
メリット③ 情報漏洩やマルウェア感染を防ぐ
シンクライアントでは、端末にデータが保存されたりアプリケーションがインストールされたりすることがなく、すべてのデータやアプリケーションはサーバー側で管理されます。
万が一クライアント端末が紛失・盗難に遭った場合でも、端末内に機密情報が存在しないため、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることが可能です。
また、端末自体ではアプリケーションを実行しないことから、マルウェアに感染する可能性も大幅に低減されます。
メリット④ 災害時にも業務継続が可能
シンクライアントは、データやアプリケーションがクライアント端末ではなくデータセンター内のサーバーに集約されて管理されます。そのため、災害が発生してオフィスの設備やクライアント端末が被害を受けた場合でも、サーバーが無事であれば業務を継続可能です。
例えば、地震や台風などの自然災害でオフィスに出勤できなくなった場合でも、自宅や他の安全な場所からインターネット経由でサーバーに接続し、通常通り業務を進められます。
シンクライアントは事業継続計画(BCP)の観点からも有効なため、災害リスク対策として取り入れるのも良いでしょう。
シンクライアントのデメリット
シンクライアントには魅力的なメリットがある一方で、導入前に知っておきたいデメリットも存在します。ここでは、シンクライアントのデメリットを3つ紹介します。
デメリット① 初期費用が高くつく
シンクライアントを導入する際には、端末の設定や調整に加えて、管理や制御のための専用ソフトウェアの導入が必要となる場合があります。
各種サービスやソフトウェアの費用が積み重なることで、特に小規模な組織や予算に限りがある企業にとっては、導入コストが大きな負担になる可能性があります。
デメリット② 安定した通信環境が必要になる
メインサーバーと従業員が使用する端末が常に通信しながら業務を進めるシンクライアントは、ネットワーク環境の品質が業務のパフォーマンスに大きく影響します。
通信環境が不安定だったり、回線速度が十分でなかったりすると、画面の読み込みに時間がかかるなどの遅延が発生し、業務がスムーズに進まなくなる可能性があります。
デメリット③ サーバー側に負担がかかる
シンクライアントは、各ユーザーのCPUやディスクなどのリソースをサーバー側に集約し、共有する仕組みになっています。そのため、多くのユーザーが同時に接続して業務を進める場合には、サーバーへの負荷が高くなります。
シンクライアントを運用する際には、サーバーの処理能力やストレージ容量を十分に確保するとともに、負荷分散を考慮した設計が必要です。
シンクライアントの実行方式

シンクライアントには、大きく分けて「ネットブート型」と「画面転送型」の2つの実行方式があります。
ネットブート型
ネットブート型は、シンクライアント端末の起動時にサーバー上のOSやアプリケーションのイメージファイルをネットワーク経由でダウンロードする方式です。
ネットブート型は、ダウンロードが完了すれば通常のPCと同じ感覚で利用できるため、使い勝手が良い点がメリットです。しかし、OSイメージのデータ量が大きいため、ダウンロードに時間を要し、端末の起動が遅くなりやすいというデメリットもあります。
画面転送型
画面転送型は、サーバー側でアプリケーションのインストールや実行、データ処理を行い、その結果をクライアント端末の画面に表示する仕組みです。ネットブート型のようにOSやアプリケーションのイメージファイルをダウンロードする必要がなく、ネットワークにかかる負担が少ないという特徴があります。
画面転送型は、以下の3つの方式に分けられます。
ブレードPC型
ブレードPC型は、各ユーザーがシンクライアント端末を通じて、専用のブレードPCに1対1で接続して使用する仕組みです。ブレードPCは、CPU、メモリ、ハードディスクなどが1つの基盤(ブレード)に集約された超小型のPCで、サーバーで一元管理されます。
ブレードPC型では、ユーザーごとに専用のPC環境を提供できるため、高い処理能力を要求するアプリケーションやグラフィック処理、CADソフトなどをスムーズに実行できるというメリットがあります。
一方で、ユーザーごとに専用のブレードPCを用意する必要があり、それに伴ってPCのハードウェアやソフトウェアライセンス、さらには管理の手間が増加する点はデメリットです。
サーバーベース型
サーバーベース型は、1台のサーバーをすべてのユーザーが同時に共有します。この方式では、すべてのユーザーが同じアプリケーションやデスクトップ環境を共有するため、高性能なサーバーを用意する必要がありません。また、初期費用を抑えることも可能です。
一方で、すべてのユーザーが同じデスクトップ環境を使用するため、個々のユーザーが自由にカスタマイズできない点はデメリットです。サーバーに不具合が発生した場合、同じサーバーを利用している全ユーザーに影響がおよぶ可能性があります。
VDI(デスクトップ仮想化)型
VDI(Virtual Desktop Infrastructure:デスクトップ仮想化)型は、サーバー上で仮想のデスクトップ環境を作成し、従業員がシンクライアント端末を通じてその環境にアクセスする仕組みです。
1台のサーバー上に複数の仮想デスクトップを集約するため、ブレードPC型のように個別のマシンを用意する必要がありません。そのため、導入や運用コストが低い上に、省スペースでシステムを構築できる点が魅力です。
また、VDI型は、サーバーベース型のようにアクセスが集中しても、他のユーザーに不具合が発生する心配が少ない点もメリットです。
一方で、仮想環境の設定や維持に手間がかかる点がデメリットとしてあげられます。また、仮想デスクトップの数だけソフトウェアライセンスが必要となる場合があり、ライセンス費用が追加で発生する可能性があります。
シンクライアント端末の種類
シンクライアントを利用できる端末の種類には、主に以下の4つがあげられます。
デスクトップ型
専用のOSが搭載されたデスクトップ型PC端末です。大きさや重量の観点から持ち運びには向いていませんが、高性能なCPUが搭載されている点や、様々な外部機器・周辺機器と接続できることから、オフィス内で使用するのに適しています。
モバイル型
持ち運び可能な薄型のノートPC型端末で、在宅勤務や外出先での利用に適しています。
シンクライアント環境では、専用のネットワーク回線が使われることが一般的です。しかし、モバイル型端末であれば、4G LTE通信をサポートしている機種も多いため、通信障害などが発生した際にも、回線を切り替えて作業ができます。
USBデバイス型
既存の端末にUSBデバイスを差し込み、シンクライアント化する方法です。USBドライブにデータやアプリケーションを集約してシステムを動作させるため、導入コストが低く、特別な技術的知識も不要な点がメリットです。
一方で、USBデバイスを持ち歩くため、置き忘れや盗難といったリスクが生じる点がデメリットとしてあげられます。情報漏洩や不正アクセスなどのセキュリティリスクを回避するためには、暗号化強度が高く、秘匿領域をもつ商品を選ぶことが重要です。
ソフトウェアインストール型
既存の端末に専用のソフトウェアをインストールし、シンクライアント環境を構築する方法です。ソフトウェアインストール型では、新たにシンクライアント用の端末を購入する必要がないため、コスト削減につながります。
また、端末の設定はサーバーで一元管理できるため、セキュリティ対策がしやすい点もメリットです。
初期費用を抑えて安全なリモート環境を構築するなら「RemoteOperator Helpdesk」
「RemoteOperator Helpdesk」は、社内ヘルプデスクやカスタマーサポート、システム保守の用途に適したリモートアクセスサービスです。「外出先や自宅から社内のPCをリモートでコントロールしたい」「システムやサーバーをリモートでメンテナンスしたい」といった場合に適しています。
VPNを使用せずに接続できるため、複雑なネットワーク設定を避けられ、手軽に導入可能です。さらに、不特定多数のデバイスからの接続をサポートしているほか、有人アクセスと常時接続可能な無人アクセスの両方に対応しているため、幅広い用途で利用できるのも大きなメリットです。
丁寧な導入サポートや30日間の無料トライアルも提供していますので、お気軽にお試しください。
まとめ
シンクライアント(Thin Client)とは、クライアント端末に最低限の機能のみを備え、主な処理やデータ管理をサーバー側で実行するシステムのことです。シンクライアントは、インターネットに接続できるネットワーク環境さえあれば場所を問わず利用できるため、自宅や外出先からのリモートワークに適しています。
しかし、費用面やサーバー側の負荷など、考慮すべき点もあるため、導入は慎重に検討しましょう。
