内部統制システムとは? メリットや構築時のポイントを解説
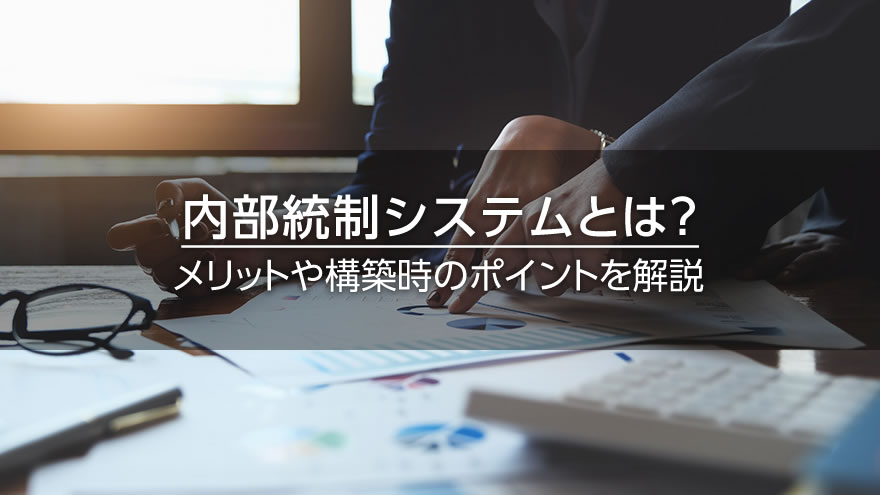
企業活動を円滑かつ健全に行うためには、コンプライアンスの確保が欠かせません。企業内部での違法行為による損失や、社会的信用の失墜などを防ぐための仕組みとして、内部統制システムの重要性が高まっています。では、内部統制システムとはどのような仕組みで、どのように導入すればいいのでしょうか。
本記事では、内部統制システムの基本的な定義やそのメリット、構築時に押さえるべきポイントについて解説します。
内部統制システムとは、企業内での違法行為や情報漏洩などを防ぐための体制のこと
内部統制システムとは、企業の内部で起こり得る違法行為や情報漏洩などを防ぐための体制のことです。企業内部における業務プロセスや情報管理の透明性を確保し、企業経営の健全性を確保することを目的としています。
特に上場企業などでは、法律によって内部統制システムの構築が義務付けられています。内部統制システムの構築義務を定めているのは会社法と金融商品取引法の2つの法律で、それぞれの条文上の定義は下記の通りです。
- 内部統制システムの法律上の定義(抜粋)
-
- 会社法(第362条第4項第6号):取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制
- 金融商品取引法(第24条の4の4第1項):当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制
会社法は、株式会社の適正な運営を目的としている一方で、金融商品取引法は、主に株主や投資家などの利害関係者に対する情報開示の信頼性の確保を目的としています。そのため、上記のように会社法では「法令・定款の適合性と業務の適性を確保する体制」、金融商品取引法では「財務計算に関する書類などの情報の適正性を確保するための体制」とされており、それぞれ内部統制システムの定義は異なっています。いずれも企業経営には重要な視点であるため、企業が適切に内部統制システムを整備・運用することは、単なる法令対応にとどまらず企業価値の向上にもつながる重要な施策といえるでしょう。
内部統制システムの目的
金融庁が公表している資料「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について」によると、内部統制システムには下記の4点の目的があります。
- 内部統制システムの目的
-
- 業務の有効性・効率性:事業活動の目的達成のため、業務の有効性や効率性を高めること
- 報告の信頼性:組織内や組織の外部への報告(非財務情報を含む)の信頼性を確保すること
- 事業活動に関わる法令などの遵守:事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進すること
- 資産の保全:資産の取得、使用、処分が正当な手続きや承認の下に行われるよう、資産の保全を図ること
これらの目的は相互に関連しており、いずれか1つの目的を軽視しても内部統制の機能は十分に発揮されません。内部統制システムを構築する際は、これらの目的につながる仕組みになっているかを確認しながら、企業全体で一貫性のある取り組みを行うことが重要です。
内部統制システムの構築が義務付けられている企業
内部統制システムは企業経営の健全性を確保するために有効な仕組みですが、義務付けられているのは一部の企業です。下記のように、会社法や金融商品取引法で定められた一定の要件を満たす企業だけに、内部統制システムの構築義務が定められています。
会社法に基づく対象企業
会社法では、「大会社」でかつ「取締役会設置会社」である場合に、内部統制システムの構築が義務付けられています。会社法上の大会社とは、下記のいずれかの条件を満たす株式会社を指します。
- 会社法上の大会社の要件
-
- 資本金が5億円以上の場合
- 負債が200億円以上の場合
なお、これらの要件に該当しない企業でも、内部統制システムの構築や運用をすることは可能です。中小企業でも、経営の健全性を確保したい場合は導入を検討してみましょう。
金融商品取引法に基づく対象企業
金融商品取引法では、有価証券報告書の提出義務を負う上場有価証券などの発行会社に対して、内部統制に関する体制の評価と報告が義務付けられています。証券取引所に上場している企業は基本的にこの対象に含まれ、毎年「内部統制報告書」を提出する義務があります。この報告書を提出するためには、内部統制システムを構築しなければなりません。
このように、会社法と金融商品取引法のいずれか、あるいは両方の要件を満たす企業は、内部統制システムの構築が必要になります。
会社法で規定されている内部統制システムに必要な要素
会社法では、内部統制システムを構築する際に満たすべき具体的な要素が定められています。詳細な内容は会社法施行規則に定められており、会社法で内部統制システムの構築が義務付けられている企業は、下記の要素を満たした体制を構築しなければなりません。会社法上で要求されている要素は、構築義務のあるすべての企業に共通する要素と、企業の種類に応じて追加される要素に分類されます。
構築義務のあるすべての企業で要求されている要素
会社法で内部統制システムの構築が義務付けられたすべての企業は、会社法施行規則第100条第1項に基づき、下記の体制を整備する必要があります。
- 会社法施行規則第100条第1項に規定されている内部統制システムに必要な要素
-
- 取締役の職務の執行にかかる情報の保存や管理に関する体制
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 使用人の職務の執行が法令や定款に適合することを確保するための体制
- 下記の(1)から(4)に掲げる体制や、その他の親会社や子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制
- 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員などの職務の執行にかかる事項の報告に関する体制
- 子会社で損失が生じる危険の管理に関する規程その他の体制
- 子会社の取締役などの職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 子会社の取締役や使用人などの職務の執行が法令や定款に適合することを確保するための体制
これらの項目は、企業の健全な経営基盤を支える基本的な柱といえます。
企業の種類に応じた特有の要素
会社法施行規則には、企業の体制に応じて追加で対応しなければならない内部統制システムの要素も定められています。
監査役が設置されていない企業においては、会社法施行規則第100条第2項により、取締役が株主に報告すべき事項の報告を行うための体制を構築しなければなりません。一方、監査役が設置されている企業については、会社法施行規則第100条第3項により、下記の要素を満たした体制の構築が必要です。
- 会社法施行規則第100条第3項に規定されている内部統制システムに必要な要素
-
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の使用人に関する事項
- 使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役から使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 下記の(1)(2)に掲げる体制や、その他の監査役への報告に関する体制
- 取締役や会計参与、使用人が監査役に報告をするための体制
- 子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、使用人や、これらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
- 報告をした者がその報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
- 監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続きなど、職務執行で生じる費用、債務の処理の方針に関する事項
- 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
これらの要素を盛り込むことで、監査役制度が有効に機能し、企業のガバナンスが強化されます。
内部統制システムのメリット
内部統制システムは、単に法令を遵守するための仕組みではなく、企業に様々なメリットをもたらす重要な経営基盤です。内部統制システムを構築、運用することによる主なメリットとしては、下記の3点が挙げられます。
リスク管理体制の強化
内部統制システムの構築により、企業は民事・刑事の両面における違法行為の発生リスクを軽減できる点はメリットといえます。例えば、社内ルールの整備や定期的な見直しを行うことで、従業員の法令違反や情報漏洩、粉飾決算などの業務上の不正リスクを未然に防ぐことが可能です。
さらに、従業員に対してコンプライアンス教育を実施する体制も構築しやすくなるため、組織全体でルールを遵守する意識の醸成にも役立ちます。結果として、企業が違法行為や内部不正によって損害を被る可能性を低減できます。
企業の社会的信用の向上
内部統制システムを構築し、その運用状況を社外に開示することで、社会的信用を向上できる点もメリットです。内部統制システムを構築していることは、コンプライアンスの意識や内部不正から利害関係者を守る仕組みが確立されている証しともいえるため、取引先、金融機関、投資家などからの信頼獲得につながります。
また、内部統制システムが機能している企業は、トラブル発生時の初動対応も早く、ダメージを最小限に抑えられる体制が整っていると評価されやすくなります。
業務の効率化
内部統制システムのメリットとして、その構築時に企業内の業務を詳細に分析して整理する必要があるため、社内業務を体系的にまとめる機会になるという点も挙げられます。このプロセスを通じて、業務フローの無駄や重複を見直し、より合理的な業務体制を整備することが可能です。
例えば、内部統制システムの構築が、業務内容を標準化したマニュアルの作成や属人化の解消にもつながり、業務全体の効率化を実現できるケースもあります。新入社員や異動者の教育もスムーズになり、業務品質の安定にも寄与します。
内部統制システム構築時のポイント
内部統制システムを実効性のあるものとして構築するには、法令や理論に基づいた基本的な考え方と、現場への浸透を意識したアプローチが欠かせません。下記では、構築時に押さえておくべき4つのポイントを紹介します。
内部統制の6要素を押さえる
金融庁の資料「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について」によると、内部統制システムは以下の6つの要素に基づいて設計・運用されることが望ましいとされています。これらを押さえた全社的な体制を整備することで、内部統制の実効性を高めることができます。
- 会社法施行規則第100条第3項に規定されている内部統制システムに必要な要素
-
- 統制環境:組織の気風を決定し、組織内のすべての者の意識に影響を与える誠実性・倫理観といった価値基準、経営者の姿勢、経営方針、組織構造など
- リスクの評価と対応:組織目標の達成に影響を与える事象のうち、組織目標の達成を阻害する要因をリスクとして識別、分析、評価しての適切な対応を選択するプロセス
- 統制活動:経営者の命令や指示が適切に実行されることを確保するために定められる方針、手続き
- 情報と伝達:必要な情報が識別、把握、処理され、組織内外や関係者に正しく伝えられる体制があること
- モニタリング:内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセス
- ITへの対応:組織目標を達成するために事前に適切な方針、手続きを定め、それらを踏まえて組織内外のITに関連する要素に対し適時、適切に対応すること
1つ目の統制環境は、他の要素の基盤として機能する要素です。また、ITへの対応については、社会や市場でのITの利用状況を踏まえながらIT環境に対応することと、ITの利便性だけでなく脆弱性や業務への影響の大きさも考慮しながら利用と統制を行うことが求められます。
全社的に内部統制システムの重要性を意識させる
内部統制システムの構築では、社内全体にその重要性を意識させて役割を明確化することも重要です。内部統制システムは、経営陣だけでなく、現場の従業員一人ひとりが意識して取り組むべきものです。しかし、従業員の中には「自分には関係ない」と感じてしまう人も少なくありません。
そのため、社内研修などを通じて、内部統制システムが自社の業務や社外への信頼性にどう関係しているかを理解してもらい、全社的に重要性を浸透させる必要があります。その上で、各従業員の役割と責任を明確にすることで、内部統制システムが形骸化せず、実効性を維持しながら運用されるようになります。
専門家に相談する
内部統制システムの構築には、法律に規定されている要件などの専門知識が求められるため、特に構築が義務付けられている企業にとっては、専門家への相談が不可欠です。
弁護士や公認会計士、内部監査の専門家などに相談することで、法令を確実に遵守しながら、実務に即した制度設計が可能になります。また、内部統制システムの法律的な側面の社内研修については、専門家に講師を依頼することでより理解しやすくポイントを押さえた研修を実施することができます。
定期的な改善と評価を行う
内部統制システムの運用では、構築後も十分に機能しているか、定期的に確認することも重要になります。一度構築すれば終わりというものではなく、構築後に実際に内部統制システムがどのように機能しているかを定期的に評価し、必要に応じて改善しなければなりません。構築・運用状況を監視して問題点や改善点を抽出する役割は、内部監査人や監査役が担います。
様々な手段を活用して内部統制システムを構築しよう
内部統制システムは、企業が健全に運営されるための土台であり、不正の予防や社会的信用の向上、業務の効率化などに効果を発揮する重要な仕組みです。特に、会社法や金融商品取引法によって構築が義務付けられている企業にとっては、法令上の要件を正しく理解し、自社に適した体制を整備しなければなりません。
内部統制は「守り」の施策であると同時に、「攻め」の経営にもつながるものです。法令への対応だけでなく、企業価値の向上や利害関係者からの信頼の獲得に向けて、適切な内部統制システムの構築・運用を進めていきましょう。
また内部統制システムの構築にあたっては、会社法施行規則で定められた要素を網羅することに加え、金融庁が示す内部統制の6つの基本的要素を意識し、ITに適切に対応することも求められます。ITを活用して内部不正などの抑止や早期発見につながる体制をつくれば、内部統制システムの機能を強化することが可能です。
例えば、インターコムの「MaLion」シリーズであれば、ファイルアクセスやWebアップロードなどを監視できるため、情報漏洩の抑止や早期発見に役立ちます。ファイルアクセス監視では、各種ファイルの操作状況(読み込み、書き込み、移動、コピー、名称変更、削除)を監視することも可能です。セキュリティポリシーに反する操作に対しては、実行を制限すると共に、不正アクセス者に対する警告も表示できる機能などもあるため、内部統制システムの構築や強化をお考えの場合は、ぜひご検討ください。
